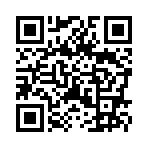2011年10月10日
川中島平俳諧研究会
川中島平俳諧研究会
9月25日(日)快晴。川中島平俳諧研究会会員9名で川中島に残る俳額、
句碑を調べるための視察研修に同行させていただいた。

北原神社の俳額は本殿の扉に鍵がかかっていて、内には入れず窓越しの
確認のみ。後日、再度訪ねる予定と聞く。



今井神社の俳額は本殿の内側、東西の欄間の上に2枚奉納されていた。
写真撮影を試みたが、墨が永い歳月に晒されていて判読、解読はなかなか
難しそう。


連香寺の俳額も文字が掠れていて判読、解読はやはり難しそう。奉納され
た額のサイズは目検討ながら80cm×250cm位の大きなものである。
桐の板面には数えきれないほどの俳句が記されている。
「明治29年(約150年前)奉納」の個所と「四季混題」の文字が読み取れる
ところを見れば、奉納した季節に合わせて句を詠んだのではなく一年を通し
て詠んだ句の中から良い作品を選んで納めたものだろうと教えていただく。


法蔵寺境内には宮本虎杖(みやもとこじょう)の花曇塚(はなぐもりづか)が
あり、自然石に彫った「念なくも 花にくもれる 眼かな」の俳句が確認できる。


更科斗女神社の俳額は本殿内3方向の欄間上にそれぞれ奉納されている。
いずれも歳月が経ち過ぎていてほとんど判読が難しい。赤外線カメラなどを
使えば、もう少し解読できる状態になるのかもしれないと会員は言う。
当時(明治期)こんなに多くの俳句が詠まれ、奉納されていたということは、
俳句が盛んであったということ。
それは多分、ほかに楽しみが少なかったからなのか、それとも松尾芭蕉が
更級紀行(1688年)で信州を訪れ、俳句を広めたことによるものなのか。
そして、このブームはこの川中島平だけのことなのか、それとも全国的で
あったのか、いずれにしても不思議な現象だという。
川中島平俳諧研究会は当初10名だったメンバーが15名に増え俳額の調査、
解読に精力的に励んでおられる。
さらに、地域の歴史発掘にも努力されている。
9月25日(日)快晴。川中島平俳諧研究会会員9名で川中島に残る俳額、
句碑を調べるための視察研修に同行させていただいた。

北原神社の俳額は本殿の扉に鍵がかかっていて、内には入れず窓越しの
確認のみ。後日、再度訪ねる予定と聞く。



今井神社の俳額は本殿の内側、東西の欄間の上に2枚奉納されていた。
写真撮影を試みたが、墨が永い歳月に晒されていて判読、解読はなかなか
難しそう。


連香寺の俳額も文字が掠れていて判読、解読はやはり難しそう。奉納され
た額のサイズは目検討ながら80cm×250cm位の大きなものである。
桐の板面には数えきれないほどの俳句が記されている。
「明治29年(約150年前)奉納」の個所と「四季混題」の文字が読み取れる
ところを見れば、奉納した季節に合わせて句を詠んだのではなく一年を通し
て詠んだ句の中から良い作品を選んで納めたものだろうと教えていただく。


法蔵寺境内には宮本虎杖(みやもとこじょう)の花曇塚(はなぐもりづか)が
あり、自然石に彫った「念なくも 花にくもれる 眼かな」の俳句が確認できる。


更科斗女神社の俳額は本殿内3方向の欄間上にそれぞれ奉納されている。
いずれも歳月が経ち過ぎていてほとんど判読が難しい。赤外線カメラなどを
使えば、もう少し解読できる状態になるのかもしれないと会員は言う。
当時(明治期)こんなに多くの俳句が詠まれ、奉納されていたということは、
俳句が盛んであったということ。
それは多分、ほかに楽しみが少なかったからなのか、それとも松尾芭蕉が
更級紀行(1688年)で信州を訪れ、俳句を広めたことによるものなのか。
そして、このブームはこの川中島平だけのことなのか、それとも全国的で
あったのか、いずれにしても不思議な現象だという。
川中島平俳諧研究会は当初10名だったメンバーが15名に増え俳額の調査、
解読に精力的に励んでおられる。
さらに、地域の歴史発掘にも努力されている。
長野県初!“キッズ野菜ソムリエ”イベント開催!
大人の遠足【飯綱高原編】 開催!
平成26年度 第1回 まちむら交流会
しの駅バルオープニング・イベント
女性就業アドバイザーによる自己分析ワークショップに参加しました
青空の会「たけのこパーティー」へ行ってきました!
大人の遠足【飯綱高原編】 開催!
平成26年度 第1回 まちむら交流会
しの駅バルオープニング・イベント
女性就業アドバイザーによる自己分析ワークショップに参加しました
青空の会「たけのこパーティー」へ行ってきました!
Posted by 市民協働サポートセンターまんまる at 12:43
│報告レポート